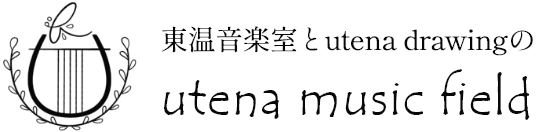【パッヘルベルのサラバンド】考察とオンラインワーク
4月のオンラインのサークルでは、パッヘルベル作曲サラバンドを使いながら、膨らむ・縮むの体感と音楽を”音楽を描く”事によって結ぶワークをしました。
パッヘルベルのサラバンド楽曲紹介
Pachelbel.Johan 作曲
作品番号:P439(T312)
suite in F# minor 1683年作曲
アルマンド クーラント ガボット サラバンド ジグ の5曲からなる小さな組曲の第4曲になります。
全曲あわせても数ページのほんとにかわいらしい楽曲郡です。
演奏
(演奏・谷中)
楽譜

パッヘルベルのサラバンド楽曲についての考察・楽曲解析
音楽史から見たリズム・スタディ(全音出版)では、サラバンドをこのように書いています。
”4分の3拍子か2分の3拍子、3拍子を2+1のように感じる舞曲が多い中で、サラバンドは1+2の感覚が強い。”
音楽史から見たリズム・スタディ(ルネサンスから現代)
これは、このパッヘルベルの曲では、メロディラインからではなく、伴奏の方にあらわれてきていますね。
この本の言っているリズムはこんな感じでしょうか。
ただ、パッヘルベルのサラバンドを体験するときには、平面的にこのリズムにのってしまうのは、なにかもったいないような気もしました。

utena drawing のワークでは、よく、膨らむ・縮む(アルシスとテーシス)ということを体験する目的で使っていますが、これは縮む→膨らむ の順で繰り返されています。
一方で、メロディのほうは、膨らむ→縮む、と逆を示していて、その立体的なリズムパターンが一緒に入ってくるところにこのサラバンドの心地よさがあると思います。
さて、このリズムパターン、実際はどうなんだろうと思って、本棚の楽譜をひっかきまわして サラバンドを探してみました。
確認できたのがこの2つ。
・ヘンデル作曲・ハープシコード組曲第2集 第4曲サラバンド
・ラモー作曲・クラヴィーアのための組曲 第3曲サラバンド

でもいろいろ楽譜を探してみると、必ずしもサラバンドがこのリズム パターンを採用しているわけではない、と感じました。そこで、実際の舞踏ではサラバンドはどのような曲として扱われているのか が気になって「栄華のバロックダンス」 舞踏譜に舞曲のルーツを求めて(浜中康子著)の中古本を購入。これいつか欲しいと思っていたので、この際。
p180に,サラバンドの典型的リズムが書いてあって、これはメヌエットと同じように2小節単位になっています。そして、上に書いたようなリズムは、この2小節目に当てはまるようです。上に上げたラモーの1・2小節の内声のようなパターンがそれに当たるのかな。(でも3・4小節でひっくり返っている。)
なんとなく見えてきたのが、
一小節目が 膨らむ縮む で2小節目が縮む膨らむ 、(あるいは逆)というパターン。
パッヘルベルのサラバンドはそれを同時にメロディを伴奏に振り分けて持ってきている感じですね。
サラバンドの歴史
サラバンドの歴史を紐解いてみると、もともとは、16世紀 スペインの植民地だったラテンアメリカに由来すると言われていて、最初は、私達がイメージする、「ゆっくりとした荘厳な舞曲」というのではなかったようです。
サラバンドの起源は、16世紀のラテン・アメリカやスペインで歌とともに踊られた民族ダンスに求めることができる。この時期のサラバンドは、表現が野卑で淫らであると言う理由から、16世紀末にスペインでは禁止となるが、実際どのようなダンスであったかは明らかではない。17世紀の初めには、情熱的な激しさと異国趣味の色彩を併せ持つダンスとして、ギターやカスタネットで伴奏される音楽とともにイタリアにもたらされた。
栄華のバロック・ダンスー舞踏譜に舞踏のルーツを求めて(浜中康子・音楽の友社)
ということで、ゆったりとした宮廷風の舞曲として定着していったのはフランスでのことらしいです。
このパッヘルベルのサラバンドがどのくらいのテンポで書かれたものかわかりませんが、通例にしたがって組曲の中の一曲として書かれているということは、やっぱりゆったり目なのかなと思います。
ゆる感がありながら、躍動感もある、生命の営みのような鼓動を私はこの曲にいつも感じるのです。
パッヘルベルのサラバンドを使ったutena drawing のワーク
4月のオンラインサークルでは、このパッヘルベルのサラバンドをお題としました。
サークルを開始して初めてのワークということもあり、とにかくまずは自分の体感を大切にできて、なおかつ心地よくそして、シンプルな構造でありながら、一筋縄では行かない複雑さ豊かさがある曲にしたい、とおもいこの曲を選びました。
自分の体感のなかから呼吸を感じ取って音楽と連動していくワークができたと思います。

参加者の感想
楽しかったです!これまで一人でやっていた時は、音楽とクレヨンの先に意識が集中していました。 今回のzoomでは最初にちぢむ・ふくらむ(アルシスとテーシス)の体験があったことで、書くのと呼吸を合わせるようになりました(一緒に参加して下さった方がzoom中に呼吸について述べられていましたが、同じでした)。アルシスとテーシスのところでは、ヨガの体験を思い出したので、呼吸を意識したのかもしれません。 右手と左手の演奏もそれぞれ描きましたが、同時にやっていても、描き手によって、線の雰囲気や強さ、かたちが違うことがわかったことも、興味深かったです。
楽しく、心地よい体験でした。 ありがとうございました! 1人でしている時とは体感が違いました。 初めてだったので、尚更だったのかもしれません。 ちぢむ・ふくらむをイメージする、描くと進めていくうちに、呼吸感やスピード感、重さ軽さなど、自分の中でバランスが取れるようになっていきました。 それが心地よかったです。 また、人によって描く線に個性があること、それが楽しいし、興味深いと感じました。 そして、ワークの後 パッヘルベルのサラバンドを弾いてみました。 身体の中に描いた時の体感が残っていて、自然に音楽の中にある呼吸を感じて演奏出来たように思います。 何度も繰り返して、ずっと弾いていたくなりました。 まだまだ奥深いご様子…これからまた楽しみです♪
参考図書
栄華のバロックダンス 浜中康子(音楽の友社)