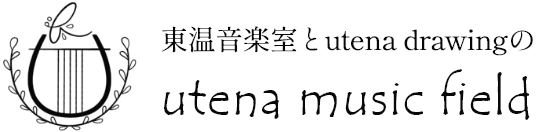utena music fieldの音楽テキストを公開しています。

実感を育てながら、楽譜に親しむワークブックを公開します。
感覚が音楽を育みます。
その感覚的な音楽フィールドに丁寧に理論やソルフェージュ体験をおろしてくるにはどうしたらよいか・・・しかもオンライン。試行錯誤しながらですが、オンラインでの活用を前提にワークブックを作成しました。
これから続くページは、そのワークブックを公開していくものです。
*名称
音楽プロセス体験シリーズ1
音楽リテラシーワークブック1
音声・動画も交えながらなので、オフラインの講座に近い感じが得られるとよいのですが。
ところで、音楽リテラシーってどういうこと?と思われますよね。これはutena music field の造語です。
リテラシーとは「読み書き」のこと。
自分の体感と音楽の諸要素が一致して、楽譜から実感で音楽がよみとれるようにしていくプロセスを共有できたら、と思っています。
私自身も実験的、勉強がてら、というところなので、このHPでの学習は基本的には無料です。
ただし、ワークブックがあります。(1800円+送料)
ワークブックの内容はそのままこのホームページにもあげていきますが、どんどん手を使って書いていってほしいので、できるだけ購入をおすすめします。動画は10分程度のものを不定期にあげていきます。反応があれば、継続する励みになります。お互いの交流が質を高めていくことにもなるとおもっていますので、ぜひ試してみてください。


これは、utena音楽室で活用をはじめているワークブックです。
作成する際に、オンラインでも学べるように、と思い、共有すべきことをこのワークブックに書き出しています。また、自分で聞き、書き、体験を積み重ねられるように、筆記部分も多くあります。
この内容はこれからこのHPにて公開していこうと思っていますが、自分のものとして学びたい、という方には、ワークブック(テキスト)の購入をおすすめします。また、動画も配信していますので、併せての学習をおすすめします。
また、このワークブックに沿って学習する中で尋ねたいことや、自分の感覚を確認したいというときには、オンラインでの個人ワークも可能です。
注意力を喚起するワークになっているので、基本にもどる、といっても、今やっているところから引き返してまったくゼロにもどるわけではなく、音楽室では現在進行中の練習にも速攻で良い影響が現れているなと感じています。
ワークブックについて動画で説明しています。
youtubeの動画配信について
HPでの「音楽リテラシーワークブック1」の公開に合わせて、youtubeでワークショップ動画の配信も行います。今の所不定期となっています。
youtubeのチャンネルは
utenaの音楽室内の 再生リスト
「ミュージックリテラシーワークブック1を使った音楽ワーク勉強会」にまとめています。
音楽ワークブック勉強会ページ案内
また、2022年から、オンライン(Zoom)を使って、講師のレッスンも受けられるようになりました。