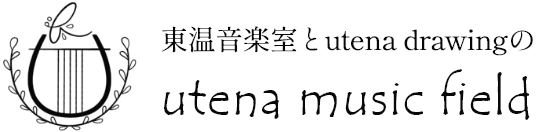音楽のみなもとをたどることとゲーテ・シュタイナーの自然科学

ゲーテの眼差し
私たち一人一人が、自然の真理に触れることは不可能なのでしょうか?
この難題は往々にして不可能の方が優勢に思われますが、それに孤軍奮闘し未来へそのいくばくかの可能性を開いたのは、ドイツの文豪でもあり政治家でもありながら自然観察研究を続けたゲーテでした。
言い換えるならそれは、
人は外に対して閉ざされた存在なのか、それとも、開かれた存在なのか、
ということ。
その問いは、たとえば教育においては、
”全ては学習によって身につくもので後天的に教えていくもの”
なのか、それとも
”自ら吸収し、理解する力が備わっていて自己組織的に育まれることが可能”
なのか、という問いにもつながるものではないかと思います。
私ごとになりますが、utena music fieldはずっと音楽が生まれる場所を求めてきました。音楽がどうして生まれるのか、誰にとっても必要なものだとしたらそれはどんな音楽および音楽教育なのか。その答えを本に求めることもありました。そしていろんな著作(シュタイナー・シュヴァイツァー・河本英夫・中村雄二郎など)を辿っていくと、いつもゲーテにたどり着くのです。一体ゲーテは何をした人だったのか、ファウストなどのお話や、多くの人々に愛されたという「野ばら」などの詩(なんと200以上のメロディが作曲されたそう)の他に、何を残したというのでしょうか。いつもそれは、森の中の正体の見えない鳥のさえずりのように、絶えず私に湧き起こってくる、音楽の生まれる場所への希求に重なってくるのです。けれど、それはずっと森の中に隠れてなかなかその姿をみることはできないままでした。
ゲーテの眼差しと、植物(有機的自然)と音楽のみなもと。
いつしか私の今世のライフワークになっていました。
シュヴァイツァーのあの音楽と世界に対する行動も、シュタイナー教育の一つ一つの不思議なやり方も、そこには自然科学者としてのゲーテの眼差しと同じ視点・認識方法が備わっていてのことだったのだと認識しています。
シュタイナーの「ゲーテ的世界観の認識論要綱」を軸にしながら、この二人の言葉を辿って、ゲーテの眼差しと音楽の可能性について、これから小さな旅をしてみましょう。

シュタイナーとシュヴァイツァー
ゲーテともなる偉人となると、とかく、人間性とか、志の高さとか、行動力とか、とにかく通常の私たちには程遠い気がします。だからゲーテの理解もそこに至らなければわからないような難しいものであろうかとか、何かすごく高尚なものなのだろうか、ともう最初からそう思ってしまいそうです。
でも、このシュタイナー・シュヴァイツァー、二人のゲーテの観察の方法をなんども読むうちに、むしろゲーテの見ていた世界はとても素朴で、体験のなかにあるリアリティをただただ辿っていくことで明らかになっていく世界なんじゃないかと思うのです。
それは、足し算足し算していたる感覚というよりは、むしろ余計なものを取り払っていけば良いし、通り道を明らかにしていけば通じていく世界線であると言えます。まあ、もちろんその余計なものは自分に身についてしまっていて引き算こそが難しい、というのは確かにそうなんだけれども・・・・
シュタイナーの「ゲーテ的世界観の認識論要綱」は、読みやすい本ではないけれども、ここに何か大事なことがあると感じていて、何度も何度も読み直してきた本です。(私は浅田豊訳のものを持っています。)そして、このシュタイナーのゲーテ論をひもとくのに、私にはもう一人の思想家の登場が必要でした。それがシュヴァイツァーです。
この「ゲーテ的世界観の認識論要綱」の作者は神秘思想家として有名なルドルフ・シュタイナー、あるいは人によってはシュタイナー教育のほうがわかりやすいかもしれません。あるいはまた、バイオダイナミック農法の創始者でもあるルドルフ・シュタイナーその人の著作になります。空間的にも時間的にも壮大な世界観を公開し、神秘思想家として名を知られることになるのは、この本を執筆したずっと後のこと、その本を書いた当時の彼は、若干二十五歳の若さでした。国をあげてのドイツの文学作品集を取りまとめる事業のうち、ゲーテの著作を任されていたころの影響下で書き上げられたものです。
この著作は、のちの「自由の哲学」へ、そして、独特の世界観へ教育へ医療へ芸術領域へと広がっていった思想の原点とも言えるもので、死の前年にシュタイナー自らが再販をしていて、それだけ思い入れの深い著作だったことが窺われます。
この本が読みにくさは、一つには、カントやヘーゲルといった哲学の理論を哲学らしく論証していく手法が一般的な書物に比べ回りくどく感じるし、また一つには表現しようとしているものが、言葉の止まるところから始まるようなものであるのに言葉を使ってその景色を織りなそうとしている困難さがあってのことだったと思います。そして二十五歳の若さ。その読みにくさをかいくぐってひもとければ…
まず、私たちが出会うのは、感覚の前に現れる経験、それも、まだ何の色付けもされていない純粋経験です。
” 純粋経験
私たちの1番最初の行為は、現実を感覚によって把握することである。この時現れる内容をまずははっきりと捉えておく必要がある。なぜなら、これだけが純粋経験と言えるからである。 姿、力、色、音などの無限の多様性が、私たちの目の前に現れると、それをすぐに悟性によって秩序づけようとする衝動が、私たちの内に生じる。私たちに現れてくるすべての個々の事象の相互関係を、私たちは個性で解明しようとする。・・・しかし、このようにして成立するものは、もはや純粋経験ではない。それはすでに経験と思考の両者の所産である。(ゲーテ的世界観の認識論要綱より)
ところで、まず純粋経験を観察してみよう。私たちが思考によってそれに働きかけずに、ただ純粋経験が私たちの意識を通り過ぎる時、純粋経験の内容とは何か?それは空間内に事物がただ隣り合って並んでいること、時間の中で前後して事物が現れることに過ぎない。全く脈絡のない部分部分の集合体である。そこに現れては消えていく対象の一つ一つは、相互に全く何の関係も持っていない。この段階においては、私たちが知覚し、また内的に体験する所事実は、それぞれお互いに全く何の関わりもなくそこにある。 その時世界は、全く均質の価値を持った様々な事物からなる多様性である。(ゲーテ的世界観の認識論要綱より) ”
うーん、難しい。 ゲーテ自体はその認識の方法については何も語らなかったので、シュタイナーはその研究から自身で言葉にしていくしか無かったはずで、ゲーテも開拓者ならシュタイナーもまた開拓者と言っていいと思います。
同じゲーテのことをシュヴァイツァーもおりに触れ書いたり、講演で話したりしています。
哲学者であり神学者でもあり、さらにオルガニストでバッハの研究家でありながら、30歳を超えて医師となり、アフリカでの医療活動をおこないながらその資金を得るために演奏会や講演を行ったシュヴァイツァーの原点もまたゲーテだったと言います。彼もなかなかの巨人ですね。熟年を迎えたシュヴァイツァーは優しく語りかけるようにこう話しています。
・・それでは、彼の世界観を作っている思想とは、どういうものでしょうか。
彼は、それをまとまった形で述べたことはありません。それらは、彼の書いたもののの中に散在しております。しかし、ごく自然にそれらは一つの全体にまとめることができます。彼の思想は、ごく単純な思想哲学であります。彼はこう考えます。真理に達するには、自然に対して何かを付け加えて考えることをせずに、先入見なしに自然に近づき、自然に没入し、自然の中に潜む秘密の幾分なりとも聞き取れるかと、注意深く耳を傾けなかればならない。自然を相手として、大なり小なり自然から何を得たかを明らかにすれば、そこに見出されたものは、人生の行路に光明を投げかけ、人間に対して精神的に生きうる養いを提供するのに十分であろう。あらかじめ我々が覚悟しておかなければならないのは、この方法では、体系の案出をはかる人々のように完全にまとまった世界観には到達することができないのであって、未完成の家に住まわなければならないということである。(シュヴァイツァー著作集6巻より 1932年 思想家及び人間としてのゲーテ)
そういうことだぞ、シュタイナー、、と言いたくなるシンプルさ。これはほぼほぼ、シュタイナーの「ゲーテの世界観」「ゲーテ的世界観の認識論要綱」や内容を言い尽くしてさえいます。
ただ、シュタイナーとは語りかける対象も違うし、そもそもシュタイナーを何度か尋ねたこともあるシュヴァイツァーはおそらくゲーテ的世界観の認識論要綱もよんでいたにちがいありません。シュタイナーが表したゲーテの認識方法をシュヴァイツァーが公の場でソフトに人々に語りかけていることを知った時には、驚きも感じましたし、ここで、わたしが興味を引いて仕方ない二人が繋がったことがうれしかったのを覚えています。
シュヴァイツァーのゲーテに関する著作や講話は、シュヴァイツァー著作集の六巻にまとめられているので、もし、シュタイナーに興味のある人はこちらも読んでみてほしいと思います。
どれだけ、二人が見ていたゲーテ像が響き合っているか、ぜひ確かめてみていただきたい。それはたまたま似ていた、ということではなく、人と人が共有できるものであることを示してもいると思います。
森の中の城壁
さて、素朴に対象にむきあい、その様を手を加えることなく受け入れることで、対象と対象が人の内面でその関わりを開示する、という、ゲーテの認識の方法ですが、世間ではなかなかうけ入れられなかったようです。
なぜなら、当時カントの哲学が流行していた中で、人は真理には到達し得ない、とかんがえられていたからです。人間の認識には限界があり、私たちはその像を見ることができるだけだ、と。けれど、対象の中に身を投じて観察するゲーテには、それは断固受け入れられない世界認識の方法でした。
私が思うのに、カントが言うのも間違ってはいない、森の中に大きな城壁があり、それは人の内面にあって、それは現在ももちろん存在しているものだと思います。もちろん私の中にも。今も。
けれどもわれらがゲーテは、のばらの痛みに思いを馳せながら森に分け入っていきます。どうもそう言うルートもあるらしい・・
芸術と認識
その筋道は、本文を読んでいただくとして、この本「ゲーテ的世界観の認識論要綱」の最後は芸術について言及してしめくくりとなっています。「科学的」を求めていた人にとっては、ほらね、やっぱりそっちへそれるのか、と思われるかもしれません。でも、そうじゃない。むしろここがど直球。世界は物理法則だけで成り立つのではない、混沌としたものや矛盾したものや、内面からもわきおこるものがあり、「創造」という人間に任された分野があります。誰もが知ることですが、人間は自由に何かを生み出す力を持っています。これが発展性を示す一方で、破壊にも繋がっていることは周知のことだと思います。この諸刃の刃である能力はいかにして人の中ではたらくのでしょうか?
その答えのヒントがここにはあると思うのです。
そこに至るには、無機的自然と有機的自然の認識方法の違いについて触れておく必要があるようです。
無機的自然と有機的自然
シュタイナー(ゲーテ)は、無機的自然(物理的なものなど)の原理は有機的自然(生命を持ったもの)には適用できないと言います。
無機界においてある現象が、法則に還元されるのに対して、有機界では原型から特殊形態が発展させられる。一般と特殊を外的に配置することによってではなく、一般から特殊を発展し出すことによって、有機科学は成立する。(ゲーテ的世界観の認識論要綱より)
力学が自然法則の体系であるのに対し、有機科学は典型の発展形態の系列である。前者の場合、私たちは、個々の法則を相互して、1つの全体へと秩序づける。後者の場合には、個々の携帯を生き生きと、順次発生させていかねばならない。(ゲーテ的世界観の認識論要項より)
物理的なことは法則が見つかればそれを当てはめて行けば良い。三角形の和が180度になることを一度発見すればそれは全ての三角形に応用できるわけです。つまり、法則に還元される、ということ。それはその簡潔さがあります。けれども生命を持ったものにそれを当てはめても、うまくいかないので、当時、有機的な法則は神のみが知るものとされていました。けれどもゲーテはそこを突っ切りました。 それが、この本で典型と訳されているものになります。ゲーテについてご存知の方は、「原植物」という概念をご存知でしょう。サボテンとバラとでは、もう全然違う、違うけれども植物たる共通した原理が働いていて、植物のおおもとはここにあり、ここから多様な植物へと発展する・・・
この原型がありそれが発展するというところが法則では捉えきれないところです。それは、ちょっと考えたら、そりゃ生き物なのだから、そうだろう、という気もしますよね。生命には遮断できないプロセスの連続性があります。それは、私自身も、薄々と感じていたものを自然農を通して、さらにリアルに感じられるようになってきたところです。
とかく、生命を物理的原理で捉えようとして、破綻が起きているのが現代と言えるかもしれないですね。生き物を生きたまま捉えるためには、法則を当てはめるのではなく、典型からのそれぞれ固有の発展していくそのさまをそのままにとらえることが必要だ、とゲーテ(シュタイナー)は訴えるのです。
芸術
“”芸術作品も自然に劣らず自然物に他ならない。””
とゲーテ(シュタイナー)は言います。
認識行為と芸術的行為の共通の基盤とは、作られたものとしての現実に対して、人間が自己自身を製造者の位置に引き上げることである。そこで人間は、創造されたものから、創造へと、偶然性から必然性へと登っていく。
・・・学問において、理念として現れるものは、芸術においては像となる。学問の対象も、芸術の対象も、この同一の無限のものであるが、ただそれが異なった形をとって現れるに過ぎない。芸術作品も自然に劣らず自然物に他ならない。(ゲーテ的世界観の認識論要項より)
さらに・・
ただ、芸術作品の場合、そこに自然の法則性が、それが人間精神に現れたと、同じ形で流し込まれているのである。ゲーテがイタリアで見た偉大な芸術作品は、自然のうちに見られる必然性の直接の刻印であるように彼に現れた。だから、彼にとって、芸術もまた、隠された自然法則の権限なのである。
学問は感覚性を全く精神えと解消することによって、これを超克する。芸術は感覚性に精神を植え込むことにより、これを超克する。学問は感覚性を通して理念を見出す。芸術は理念を感覚性の中に見いだす。この心理を包括的に表現しているゲーテの言葉を引用して、私たちの考察を閉じることにしたい。
「学問とは、一般的なものの知識、抽出された知と名付けられるだろうと私は考えている。これに対し、芸術とは、行為に応用された学問であろう。学問が理性であるとすれば、芸術はその機構(メカニズム)であり、故に、それは実践的学問と名付けられる。そうすれば、結局学問は命題であり、芸術は課題であろう。」(ゲーテ的世界観の認識論要項より)
もういちどシュヴァイツァーの言葉にもどってみましょう
彼は、それをまとまった形で述べたことはありません。それらは、彼の書いたもののの中に散在しております。しかし、ごく自然にそれらは一つの全体にまとめることができます。彼の思想は、ごく単純な思想哲学であります。彼はこう考えます。真理に達するには、自然に対して何かを付け加えて考えることをせずに、先入見なしに自然に近づき、自然に没入し、自然の中に潜む秘密の幾分なりとも聞き取れるかと、注意深く耳を傾けなかればならない。自然を相手として、大なり小なり自然から何を得たかを明らかにすれば、そこに見出されたものは、人生の行路に光明を投げかけ、人間に対して精神的に生きうる養いを提供するのに十分であろう。あらかじめ我々が覚悟しておかなければならないのは、この方法では、体系の案出をはかる人々のように完全にまとまった世界観には到達することができないのであって、未完成の家に住まわなければならないということである。(シュヴァイツァー著作全集第六巻より)
結論はない、可能性だけはある、だから、よくよく観察しその道をいけ、とシュヴァイツァーは語りかけてくれているように思います。
さらにシュヴァイツァーの言葉に耳を傾けてみましょう。バッハの演奏家として若い頃からその性能を発揮していた彼の言葉です。バッハ、あの込み入った構成は機械が演奏しても美しいけれどもそれを自然に演奏することはなかなかに難しいことだと思います。そして、彼の演奏にはそのおおらかさと人間味のある深さを感じます。その彼からみたゲーテ・・・
ゲーテは見る人でありました。
彼は形象によって語ります。
これは、彼の表現法の特徴としとて、彼自身すでに、青年時代に認めていたことです。
彼は言葉で絵を描く秘宝を知っていました。
私たちは、彼が見、そして私たちにもみさせようとするものを、見るのであります。
もう一つの特色は、彼は、高い響きやものものしい形容詞で効果をあげようとする芸情的な詩語で語ったのではなく、全く素朴に日常語によって表現し、そして、それに情熱を与えることができたということであります。
さらにもう一つの彼の言葉の特徴があります。
リズムであります。
通例、彼の文のリズムは、詩句のリズムと一致しません。
両者は緊張関係を保っております。
その点では一種の血縁関係が彼とバッハのあいだにあります。
すなわちバッハにおいては、主題は拍節のリズムやアクセントに合わせて考えだされたのではなく、自分自身の道を歩んでいるのであります。
・・・彼の詩句は一種の高次の散文のような感じを与えます。 それが彼の詩句に驚嘆すべき自然さと気品を賦与しているのであります。(シュヴァイツァー著作全集第六巻より)
物理的な法則性からはこぼれ落ちてしまう、生命。それでも、生命を法則性で捉えようとして現代の問題があるように思います。 そしてそこに、病の苦しみや、社会の行き詰まりや自然との共和の難しさが、まさに。
ひとつ、音楽でも。
音楽は音と音の間にこそ生きていて、人の音楽体験も音から音へのプロセスに宿ります。例えば絶対音感という物理的な確信があれば、音楽を克服できるかのように煽る向きがありますが、本当に音楽と自分が出会おうとするならば、多分、そこではないのです。
今回、この本「ゲーテ的世界観の認識論要綱」を取り上げるにあたって、「思考」と「人間の自由」については書ききれなかったのですが、じつはそこを通ってこその、この理論の全体性があるので、機会があればぜひ読んでみてください。そして、一度で理解できるものではないので、手元において、何度も読み直してみてください。
ゲーテと未来
そう、そして、もちろんゲーテの認識方法は人智学(アントロポゾフィー)だけのものではなくて、私たち誰もにとって必要な認識方法で、それをこの本にまとめあげたのが、まだ若きシュタイナーでした。
ゲーテの認識論は、というか、そのころに一人の意識に芽生えたこのあたらしい認識は、その後、どうなったでしょうか。もちろんシュタイナーのその後の活動の支えとなっていったはずですし、もっと広く、さまざまにみえるところ、見えないところに影響を与えていくことになります。例えば、もしゲーテが先んじていなければ、ソシュールの言語学はうまれていなかったかもしれないと(あくまで個人的に)思います。また私が一時期どっぷりはまり込んだオートポイエーシス(自己創出)は、その日本の先駆者の河本英夫がおりに触れゲーテについて書いていて、その影響力を感じます。おそらく探せば、意識的であれ、無意識であれ、影響を受けた人はおおいでしょうし、ゲーテと接点がなかったとしても、すごくこれはゲーテ的な発想だなと思わされることに出会うこともあります。つきつめれば、そうなるのは当然だろう、というような。
私自身についてですが、これから少しづつ、シュタイナーについても書いていくことがあるかと思います。私は彼に深く影響を受けた人間ですし、私の仕事にも深く関わってきています。シュタイナー関連の学校をでたわけでもないので、もしかしたらどこかから批判もあるかもしれない、けれどもやっぱりここは外せないところなのです。まちがっているかもしれない、けれど決して中途半端にとりいれようとしているわけではないことを、理解してもらうためにも一度書いておかなければ、と言う思いがありました。私の原点もまたゲーテにあります。

最近のワークショップ
関連記事