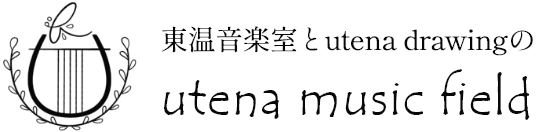【スカボロー・フェア】utena式楽曲解析
スカボロー・フェア(Scarborough Fair)、といえば 私達昭和世代だと、サイモンとガーファンクルの美しいハモりとチェンバロの伴奏の曲が思い浮かびますが、原曲は16世紀イングランドの伝統的な民謡だそうです。
スカボロ・フェアはドリア旋法
どこか懐かしいような神秘的なような気分になるのが、
歌詞の
パセリ・セージ・ローズマリー &タイム
の ”マリー”のリ の音
(音階の第6音)の不思議な上がりかた。独特の浮遊感があります。これは、普通の短調と違って、この6音が高い ドリア旋法でできているからです。そしてこの曲の中ではここにたった一つ。これがあるために、
parsley sage rosemary and thyme
ということばはまるで魔法のことばのように聞こえます。
ドリア旋法は、別の記事で取り上げた「グレゴリオ聖歌過ぎ越しの犠牲」と同じなので興味のある方はこちらをどうぞ。
改めてきくとこの2曲はほんとうによくにています。
実は前にドリア旋法を講座で取り上げたあとに、受講者の方から、「スカボロー・フェアもドリア旋法ですね!!」と御連絡頂いたのです。よく、結びついたな−と感心しました。
スカボロ・フェアをめぐる話
スカボロフェアが導いた、楽しみを希うこころとの出会い
また、こないだある方と話題にのぼった、 ピアノレッスンという映画の The Heart Asks Pleasure First(楽しみを希う心)も最初のフレーズはドリア旋法になっています。(最終的にはこの曲は導音に導かれる短調でフレーズが閉じはしますが・・)
その方は私がお店においてあったピアノでスカボロー・フェアを弾いたときに、実はこの曲がとてもスキで、と、楽譜もってこられたので、たまたまかもしれませんが、でも、無意識でなにか、近いものを感じられたのかな、と思いました。皆さん、理屈なんかでなく、感性でよくきいておられるんですねー。
それを紐解く私が無粋なような気もしてきます。
レミファソラシドレ という並びの音律(昔はドから始まる音階だけでなく、レとかミとかファ・ソ・ラから始まる音階などがありました。)のレがフィナリス、ラが支配音・・これも忠実に守られています。
2017年の5/6月の入門講座では音高のワークの後、scarborough fair を使ってメロディがレーラーレの間を行き来している感覚を取り出してやってみました。
フィナリスと支配音の関係は、ドミナントと主音に類似しています。人が感覚的に音楽を生み出していくために一番自然な関係性なんではないかなと思うのですね。これが体感的につかめていると、音の流れの必然性が理解できるので、こういうのを繰り返し入門講座ではやっていくことになります。
*注、2021年現在、入門講座はなくなっています。その代わりに、月600円でnoteにてオンラインサークルを開催しています。zoomを使ったワークショップと動画でのレクチャーで、入門と同じ内容のものに毎月ご自宅から参加することができます。
詳細はコチラ(noteのサークルページに飛びます)
庭にある、スカボロフェアのおまじないの植物
全く、話は音楽から横へそれてしましますが・・・
息子が、台所に干したハーブを入れてパスタをつくりながら、スカボロフェアを鼻歌で歌っていたのはいつの昔のことだったか。
うちの庭には、parsley sage rosemary and thyme が揃っているので、ちょっとご紹介です。

パセリ 
セージ 
ローズマリー 
タイム
んんー、いい香りが漂ってきそうです。
市場の雑踏、ハーブのかおり。
そこに住むかつての恋人、叶わぬ思い・・・・
歌詞は切ないですね。

スカボロフェアをうたう 拍の質感の違い
さて、個人レッスンでも取り上げたときは、これだけではなく、拍子としての繰り返しの流れ(オスティナート)を、どんな風に捉えたら演奏のとき気分が出るだろう、ということで、いろいろやってみました。
参加者さんと私、お互いの頭のなかにあったのは最初はあのサイモンとガーファンクルのうたです。
柔らかにでも、推進力がありながら、ゆるみもある、タータタータという繰り返し。出始めは上向き?下向き?じゃあ自分で演奏するとしたらそれはどうなる?ということなど・・
で、
今あらためて ケルティック・ウーマンの演奏も聞いてみました。S&Gは3拍子の拍も聞こえてくるけれども、ケルティック・ウーマンの方はタータの流れの方が有勢。ケルトの3拍子、ですね。まさに。
S&Gとケルティック・ウーマン のオスティナートを描きとったものが下。
どちらも上の方はまだ探している感じ。下に行くほど、感覚がつかめてきてる感じでした。
紫と青、どっちがどっちでしょう?