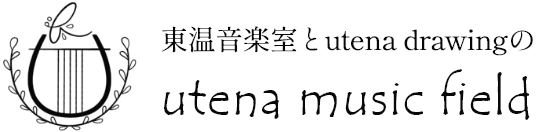リズムが人と合わないという悩みに、utena drawingを活用して、リズムの理解を体験していく

誰かと演奏をしたくても、何かが追いついってってない、自分がはいるタイミングがわからない、という方。いろんな方のレッスンをしてきて思うのは、その悩みは、多くの人にとって共有のものだということ。
それはどうしてなのか、utena drawingをやり重ねるうちに見えてきたことがあります。そしてそれを修正していくアプローチもまた、utena drawingで。
utena drawingは音楽を描いて体験することで実感に繋げていくワークで、utena music fieldが発信源。

演奏中自分が入るタイミングで迷う、というmさんの悩みと願い
音楽室で個人ワークを受けていただいているmさんを例に。
mさんは、ある楽器愛好家グループで、素敵な小さな弦楽器を練習しています。
楽譜を読むのがちょっと苦手、そしてグループで演奏するとき、自分の入るタイミングがわからなくて迷う、ということで、うちの音楽室の戸を叩いてくださったのでした。
うちの音楽室では、どんな希望を持っておられるのか、どんな悩みを持っておられるのかを最初にお伺いすることにしていて、その対話を元にワークの内容を決めていくことにしています。mさんとのお話から「音楽をもっと楽しくしたい。」根っこにはそんな思いも持っておられます。「音楽をもっと楽しくやりたい」、それは多くの人が抱く普遍的な願いですね。それが楽譜やリズムの壁で一歩先へ進めないのは歯がゆい思いがしますね。
演奏のタイミングでつまづく理由と、その原因
リズム苦手さんの楽譜の読み方
さて、今は、そのグループでやっているある曲を(曲は内緒でお願いしますとのこと)練習中。
まずは聞かせていただきました。初めて取り組む曲。音程はとても丁寧に拾って読んでいるようでしたが、聞きなれない曲だしリズムが難しい。
私の受けた印象では、タイミングがわからないのは楽譜が読めないというよりも、mさん、リズムに不慣れだなと思います。なぜなら、楽譜を読む時、音符を最初っからひとつづつ拾って読んでいるからです。
(下の楽譜はウェルナーの野ばらで実際持ってこられた曲ではないのですが・・)
ソーソーシーラーソー(じっさいはもっと読めてましたがでしたが、ちょっとおげさにこんな感じ)

ね。私も〜と思う人多いでしょう?
なぜ、こうなるのか、なぜこれではリズムが掴めないのか、ということなんですが、先に結論をいうと
・リズムの仕組みをイメージできない
のです。mさんだけじゃなく、ほんと、多くの人がここで路頭に迷っていると思います。
学校で、一拍とか、二分音符は2拍とか、8分の6拍子は8分音符が一拍・・・といった情報は確かに教えてもらったけれど、右から左へ抜けていきました。とか、いままでピアノは耳コピでがむしゃら頑張ってきました。という人がほとんどなのですが、楽譜を流れよく読んでいこうとするなら、これらのリズムの仕組みが頭でわかるだけでなくて、生き生きとイメージできるようになるといいんです。
まずは拍の鼓動を体験すること
リズムは「拍・拍子・リズム」の少なくとも3重の構造になっています。となると、ややこしくて難しそう、と思うかも知れないのですが、それは逆で、拍、拍子の支えがあるからリズムが見えてくるのです。

音符の長さだけの連なりで読もうとするから、あやふやになって、自信がなくなってしまう。リズムというのは、音符を順番に正確に定量的に割り振っていっても、それらしくならないもので、どっかで計算間違いがあったり、休符が読めなかったり、アンサンブルになると他の人の音が聞こえなくなったりします。だから、一つ一つの音符のながさを繋げていくのではなくて、まずはその曲の鼓動である拍や拍子に慣れてもらうことが重要なのです。
もし、それが体感的に理解できるようになったら、まずは、その音楽にリズム的に同調していく、ということができます。
何はともあれ、
まずは拍、そして拍子。

utena drawingを使って、対話もしながら、細やかに動きを体験していきます。
つまづくところで、手が止まってしまう、というのを丁寧に補正して、イメージと体験が繋がるようにutena drawingを使います。
mさんの場合、月に1回、対面でのワークを続けていきました。同時に音楽の仕組みについても「音楽リテラシーワークブック」の順に少しづつ体験=理解という積み上げをしていきました。
そして、mさんの希望は、グループの中で自分のパートが無理なく演奏できるようになること。段階的にはまだ次のステップが必要なようです。
そこで並行してやっていったのが流れを掴んでいくオスティナートワーク

そうすると、誰かとリズムを共有する心地よさが生まれてきます。
そこにリズムの知識を組み込んでいきます。
アウフタクト(弱起)、付点リズム、休符、など、楽譜の中の具体的なリズムの長さを、育ってきた拍・拍子の感覚から導きだすのです。
テンポの揺れなどもutena drawingならば、その辺の自由がききながら、拍・拍子・リズムの原理に体験的につながっていくことができると思います。
なるほど〜と思いました。との感想。
楽しんでいただけたらOK!
mさんのその後
mさんは、そのグループで出会った新しい曲をいつも大事そうに持ってこられます。
その度に、拍は、拍子は、全体の流れは?自分のリズムは?と繰り返してやっていくことで、周りの音が聞こえるようになってきたり、自分の出番のタイミングに戸惑ったりすることが乗り越えられたりして役立ててもらってる様子。その曲だけできるようになるんではなくて、音楽そのものへの感覚が広がっていく方向づけをしてあげられたらと思っています。
お役に立てて何よりです。☺️
リズムの仕組みを描いて体験するワーク
mさんが時間をかけて行なってきたような、リズムの仕組みを描いて体験しながら、理解に繋げていくワークショプ、東京で行います。
utena drawingの活用方は他にも・・
- リズムが人と合わないという悩みに、utena drawingを活用して、リズムの理解を体験していく
- ベートーヴェンソナタ悲壮の3楽章・長い音符を的確に捉えるためのutena drawing
- 大人ピアノレッスンのためのドローイング・ショパンのノクターンop9-2
- ベートーヴェン「喜びの歌」メロディドローイングワーク
utena drawingは音楽プロセス体験理論を背景にした、描いて体験する音楽ワークです。音楽プロセス体験は、音楽は音の点のところにあるのではなく、音から音へのプロセスにあり、人の体験もそこに宿っている、という考え方のもと、描いて解像度を上げて可視化して理解していくものです。なにより、楽器も楽譜も後回し、気楽に楽しく始められるのが良いところ。
東京WSに間に合わなかった方、東京まで行けない方は、オンラインのコミュニティはいかがでしょうか?