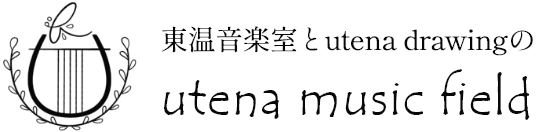リズムが取れない理由とリズム感をとり戻す方法(1)

はじめに
一般的にリズム音痴を矯正するために使われている方法の多くは、身体を固めてしまい、かえってリズムを取りにくくしてしまっています。
なぜでしょうか。
それは、それらの方法が、リズムがとれた結果をもとにしているからです。
では、リズムが取れる感じはどんなものか、そもそもリズムとはどのような存在なのか、結果ではなく、音楽の原体験に立ち返ってみると、リズムというのは一般的に言われているものとは違った姿を見せてくれるでしょう。
東京ワークショップの特別集中グループワーク「リズムとは?」の開催に先駆けて、リズムがわかる、わからない、その理由と構造、どうすればリズムの体感が掴めてくるのか、ということを5回に分けて記事にしていこうと思います。
その前に、私とこのワークの紹介をさせてください。私は、utena music fieldにおります、谷中と言います。音楽を「動線を描く」ことによって、音から音への移動の感覚を動的にとらえ、体感に結びつけていくutena drawingという方法を使います。音を点と点ではなく、そのプロセスを描くことによって距離感を掴んだり、解像度を上げていくのです。

その方法を使いながら、リズムとはどんなもので、どんなふうに感じ方が変わったら、その景色が見えてくるのか、ということを説明していきます。
4つの誤解と無理解
これまででリズムが取れない、という人とutena drawingをやってみてさまざまなことがわかってきました。utena drawingはその人が感じているものがそのまま現れてきます。リズム感がないとは思っていない人も、リズムが平板で表現力につながらない、拍がガンガンきちゃって、メロディが聞こえない、とか、いろいろ音楽的な通りの悪さも見えてきます。
でも、本来音楽のリズムって、いきいきとして楽しいじゃないですか。気分を運んでくれるじゃないですか。なのに、いざ、リズムを取ろうとすると、そうはいかない。身体が止まってしまうんですね。でもほんとうはその、気分いい、ままでいいんです。
ただ、音楽のことを、もっと知ってあげてください。 自分が、ではなく、音楽をもっと理解し共有できる世界線へ自分を持っていってあげてほしいのです。聴覚を賢く育てる。そうすると音楽はあなたの身体を音楽的に運んでいってくれます。
いままで見てきて、多くの人がリズムに対していくつかの誤解があり、それを体験するのにも、間違った方法で付き合っていこうとしています。
なので、リズムに対する動的な理解、それから、それを体感に繋げていく方法。
それをこれから4つの記事で書いていこうと思いますが、今回はその内容をザクっと書いておきます。
・リズムは点ではない

楽譜がなければ音楽は共有できないのですが、楽譜は音楽のすべてを描き取ることはできません。なので、音符という点を使います。でも、音楽の実際はその点から点の間にあります。ここが第一の誤解のもと。音が点だと思っていると、次の音は突然現れてきたように感じてしまいます。なのでぎくしゃくしていまう。・・・これを音から音へのプロセスとして体験するには・・・・
・拍は脈。音楽の鼓動
リズムについて知ろうとするには、まず拍のことを理解・体験しそのイメージをまずはしっかりと掴みましょう。拍は音楽の鼓動です。機械的でない、柔らかい拍もあれば、鋭い拍もあります。そして、拍をもとにリズムは積み上げられていますから、それを体感でしっかり身につけておくことが大切。なのでその方法についても解説していきます。

・ビートの常識は身体を固めてしまう
一般的に使われているビートの説明、強弱弱、とか強弱中強弱、とか、アップダウン、前うち後うち、という言い方、そしてその言い方を正解として身体をそれに合わせてしまう、という方法は、実は身体を固めていってしまう方向に向きがちなのです。そうではないやり方でビートを感じることができます。

・リズムはリズムパターンで身につける
リズムは複雑そうですが、順を追って体感で覚えていけば、いくつかのリズムパターンの応用で大概はいけてしまいます。そしてリズムは拍が基準となっているので、ここで改めて拍感の重要性がわかると思います。
体感的に理解しておくべき基本的なところはこれだけです。

やりこんできたことをリセットする
ただし、大人の場合、この方法を取り入れようとした時に、やりこんできでしまっているものが邪魔をしてしまうことが往々にしてあります。時間を見る視点が変わってくるので、それを掴むことも難しいと感じる人がいます。
その体感から、上記のような体感へシフトするのには、パラダイムシフトが必要になる時があります。すぐにシフトする場合もあれば、なかなか時間がかかる場合、体感そのものに関わるので、気分的な不快感や苦痛を感じることがあります。これはutena drawingの特徴でもあります。自分に違和感がはっきりと感じられるのです。時間をかけて解凍させていく、という方法もあります。
そこをクリアすれば、単に一曲のリズムが取れるというのではなく、どんな曲へも応用が効くようになり、スムーズにリズムをとることできるようになるでしょう。
理解できたものを身体化する
音楽のことを理解することの大事さは説明しました。
理解できてからやることは、それを聴覚をともなった身体化、です。いろんな曲で取り組んでみるのが良いと思います。
リセットすべき体感が戻ってくる人は、誰かについていて練習を重ねる方が良いかもしれません。
実際、リズム感の良い人と一緒にリズムうちをすることは、とてもよい身体化につながります。
utena music fieldでは対面とオンラインで学習を進める方法も提案しています。が、これから書いていく記事にもあなたのリズムに対する悩みに対するヒントがあるかもしれません。リズムに対して困りごとのある方、あるいはリズムの曲の強い生徒さんにどうアプローチしていくか、の見通しがつくかもしれませんので、引き続いてご覧いただくと嬉しいです。
・・・ということで、2回目はリズムは点ではない、というお話をさせていただこうと思います。
その前に・・・
リズムに関する以前の記事をどうぞ。
ワークショップはこちら
その他イベント情報