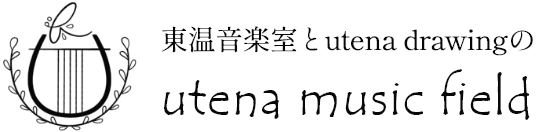ブルクミュラー「せきれい」の音楽体験と軽やかな演奏のための考察とutena drawing

せきれいの俊敏さ可愛らしさを共有したい曲
ブルクミュラーの練習曲集の11番「せきれい」は、野生の小鳥せきれいをイメージして作曲された曲です。
実際、せきれいを観察してみてからこの曲を弾くと、改めて、ブルクミュラーさんの「ね?そうだよね。」という声が聞こえてきそう。セキレイの可愛らしさが音になって表現されていて、いつ弾いても楽しい曲です。
さあ、でももし生徒さんにこれを伝えるとしたら・・・
どんな生徒さんに、どんな現場で、誰が伝えるか、で、それはもちろん、ちがっていいとおもうのですが、うちの教室にありがちなのは、この曲が「重くなってしまう」ということかなと思います。
なので、それを前提に
ブルクミュラーさんが捉えたセキレイ🟰楽曲理解ということをやっていってみようと思います。
セキレイっぽく弾いてね、もっと軽く弾いてね、というまるなげではなく、ですね。
それじゃ、なにも教えたことにならない。
どうしたら軽いセキレイのような動きがピアノで再現できるのか、そのプロセスを生徒にてわたしできるのでなければ。
まずはせきれい観察
7月の台レッスン研究会では、参加者Uさんが、生きた小鳥せきれいについての資料をたくさん集めてきて見事な発表をしていただき、その熱がオンラインでつたわってきました。それによると、インコほどの小さなことりですが、その身体能力は抜群で、地上でも空でも、実に俊敏に動き回る鳥なのだそうです。インコやスズメなどとはかなり違う動き方をしますね。
Uさんは手のひらを鳥の羽根に見立ててその様子を再現してくれて、もう、とっても嬉しくなりました。
最近は都会でも目にするとても身近な鳥ですが、200年まえのブルクミュラーさんの身近にも同じセキレイがいたのかと思うと時代こそ違っても、この地球上でつながっている不思議な感じもします。

そしてその動き、セキレイのことを知れば知るほどに、まさに、この楽曲は見事にいいあてています。
なんとなく、可愛い小鳥の雰囲気、というよな、漠然としたものではありません。
ブルクミュラーさんは、間違いなくその目で、この鳥を観察して作曲したものにちがいないと確信できるような、見事さです。
なので、この曲を演奏したいと思う人はぜひ、何はともあれ、せきれいに会いにいってみてください。
(全音出版社の北村智恵氏の解説では、2本の足を揃えて同時に前に出す小鳥独特の仕草、に例えています。解釈はいろいろだと思いますが、セキレイはとにかく走る鳥です。そして素早く飛び立つ。その忙しさが、下降や上向の幅の広さに表現されていると私は思いますし、インコやスズメのようにちょこんちょこんと動く鳥ではなく、立ち止まっても一瞬、それはこのメロディに続くスタッカートの和音に現れていて、そこはブルクミュラーもよく観察していたのではないかなと思います。この鳥の仕草の捉え方のイメージ作りで、きっと表現も違うものになるので、スルーできず、ここに書いておきます。どちらを選ぶかは自由ですが、ここからの曲作りは、漠然と小鳥、ではなく、実際のせきれいをイメージしたものとなっています。)
軽やかな演奏のために
1 動機のモティーフについて

リズムの捉え方の問題
生徒さんをみてると、最初のこの4つのタカタンが重くなりがち。
よく聞くと、ソミドのドが大きくて重い。親指だから手の重みのままに弾くとそうなってしまう。(人間の手には羽が生えていないので・・)これをふわっ、ささっ、とセキレイのように弾くために二つのフェーズへのアプローチを考えます。つまり、リズムの捉え方の問題、と、メカニックの問題です。
演奏が重くなるのは、アウフタクトのように聞いてしまっている、ということが原因になっている場合もおおきい。ソミドのドが拍の頭にきているイメージ。
あるいは二拍子の「1と2と」の「と」が大きくなっている(日本人あるある)。
たんに軽く、というのではなく、この拍子のなかの一拍の中に入れ込んでしまう、コンパクトなこのリズムの性質をよく感じ取ることが大事。また、一拍ごとに同じ動きを繰り返しながら下降してくるこのせいれいのようすは、あっというまに遠くから目の前に来たような感じで、スタッカートで立ち止まるのではなく連続性でつかめるとよい。そのあたり、流れの掴み方自体を変えていくためにutena drawingをつかって、全体の流れを掴んでいくことが効果的だと思います。
メカニックの問題
一拍の中にこの小さなモティーフを入れ込むための手の状態。
前提として、手のバランスが整っていて、5指がしっかり小鳥の足のように立ち、親指の付け根がやわらかく、3度、4度が咄嗟に動きに変換できること。
手の柔らかさについて力のバランスについては日頃のテクニックの練習から意識しておく必要があります。また、3度、4度の幅感(タッチと音程感両方)を育てておくことも大事。これらは日頃の取り組みが、難しいパーツも楽に乗り越えられる鍵になるので、日頃のテクニック練習では、逆にこういうことに対応できる身体をイメージしてやっていくといいと思います。(何を使うかより、どう使うかが問題)
2、音程の大きな動きと小さい半音の動き
最初の2小節のような大胆な動きと、その次にやってくる和音はよく見ると内声と左手が半音階で降りてきている。セキレイの一気に高いところをから降りてくる感じと、ちょこちょことした細かい動きに同期してたのしい。 どこでそれが切り替わるか、は意識しておきたいところ。生徒に考えさせてもよいかも。あるいは先生がいかにもで楽しげにそれを表現してみる。

その二つの動きの交代は14小節まで続きます。
みていて飽きないせきれい。
3、流れから軽さを掴む
最初のモティーフが重くなるタイプの人は、流れを上手く作っていけない、ということもあります。そういうときは逆にそのモティーフから意識を離して、音楽の流れに乗って遊んでみるのもいいですね。ということで2小節単位でのutena drawingオスティナートワーク。
この場合はあまり忙しく感じなくてもちゃんと音楽にのれるよ、というところで2小節を選んでいます。

4、大まかな構成を掴む
少し視野が広がってきたところで、この曲のストーリーに目を向けてみましょう。
しっかり楽譜を俯瞰して、フレーズのまとまりとつながりを感じながら、そしてこのストーリーを感じることをしっかりやります。それを前提として、utena drawing。うまくつながったら、自分でも納得がいくし、逆に曖昧だったところをutena drawingが教えてくれることもさいさいあります。

さらに音楽はどう進んでいくか
5、タカタンの変化形
15小節からの右手のメロディも原型はタカタンでそれを引き伸ばした感じ。 これに気づくのはなかなかかも。

6、半音はどこまでか
半音の進行はどこで始まって、どこで終わるか。どこでどんな動きから別の動きに変わったかを明確にしていくことで、せきれいのうごきはさらにリアルになる。
7、 大きなメロディのアーチ
19〜22は1〜2小節を逆に飛び上がっていく感じ。ここではさらに一オクターブの飛翔があって、最終的にはヘ音記号のドまでいきつく。

1〜2小節の類似は最後に26〜27小節にもある。ただしここはトニックとドミナントの繰り返し。二匹のせきれいの息があってきたのかも知れないし、終わりが近づいている、合図のよう。
8、2番カッコへの飛び込み

2番カッコがつけたしにならないで一気にそこへ流れていく感じにするには、15小節リピートから最後までの構成を掴んでおくことが大事。。けっして2番カッコから始まるのではない、ということ。
9、ドミナント・トニックの呼びかわし
2番カッコからはまるで二匹のセキレイの呼びかわしのよう。
右手のトニックに対し、左手がドミナントでかえす、を繰り返して、結局二匹で両方さわぎ倒す。
22小節目〜25までは2拍ごとだったのが、その次から1拍度とになりしかもユニゾンになり まあ、かしましい。
10、終止
そんなこんなのセキレイの夫婦を楽曲としてどう終わらせるか、が最後の二つの和音できまってきます。さて、あなたならどうやって終わらせたいでしょう?
その決定の気持ちや意思が、この楽曲に対して演奏者がイニシアティブを取るということ。
演奏してみました!
目標は、いかにセキレイらしくできるか、です。
実家の古いピアノで弾いています。
まとめ
タカタンのリズムが重くなる現象をメカニックという一つの「解決」で終わらせず、そこからセキレイの観察へ、音楽へと広げていくのが音楽プロセス体験の醍醐味だと思います。そして、この曲はそれに耐えうる内容をもっていますし、子供を飽きさせない本物感もあります。
文章で書くとどうにも説明的になってしまうけれども、これをいかにあたらしい世界が広がっていくかのように共有していくか、教える側としても興味が尽きないところです。一緒に感じたり驚いたり、考えたりしながら。
最終的にテンポはその生徒にあったテンポを選んでいけば良いのです。
ブルクミュラーに行きつかない生徒さんでも、思春期に差し掛かると、こういうことを楽しいと思うようになります。音楽の深さに触れさせてあげたいですね。また知的な遊びとしての提示。でも高尚なものではなく、暮らしの中、そう身近なセキレイの動きと音楽との接点のような、むしろ見逃されそうなちいさな発見のなかから浮かび上がってくる世界との遊び方に触れてもらいたい。音楽だからこそできることだから。
描いて学ぶ、遊ぶ、utena drawingについてはこちら
オンラインで学ぶ
・マガジン月額600円
・発展コース3200円 ・発展プログラム8000円
音楽教室の先生や指導につかいたいかたはかならずこちらをごらんください。