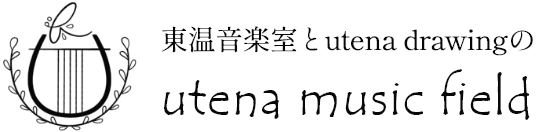バッハが描いた不思議な線
平均律クラヴィーア曲集第1巻のバッハ自筆の表紙に描かれた線の謎について

平均律クラヴィーア曲集の表紙は音の記号を暗示したのか?
wikipediaで平均律クラヴィーア曲集を検索すると、その第1巻のバッハ自筆による表紙の絵と文章を見ることができます。気になるのは、この、くるくると描かれた線。今回は平均律そのものではなくて、この表紙絵の不思議な線について、私なりの考察を書いていこいうと思います。どうしてバッハはここにこんな線を描いたのか、これはただの飾りなのか、それとも何か深い意味があるのか・・気になりますよね。

wikipedia《平均律クラヴィーア曲集》
平均律の表紙絵は、音律の暗示なのか
バッハ作曲の平均律クラヴィーア曲集第一巻に描かれたバッハ自身が描いた線は何かの暗示なのでしょうか。
ある音楽研究家によってうこのうず巻き装飾を通じて音律と調律法に対する指示を出していたと言う説が浮上し、1部の人たちに支持されてきた(wikipediaより)ようです。あの渦巻き模様がcやgをあらわしているというのです。
少し拡大してみてみましょう。


本当にそうなんでしょうか。
わたしはちょっと違うんじゃないかなーと思っています。
バッハの鼻歌が聞こえてきそうな線
私が考えるのは、バッハはもっと気軽にちょっとした装飾として、鼻歌混じりにペンを持ち、まるで演奏を楽しむ人のように、鼻歌に合わせて描いてみせたもの、だったように私には思えてなりませんでした。
そしてそれは、たんなる飾りであると同時に、何か音楽的な仕草であり、バッハはそれを自然に表すことができたのではないか・・
なぜなら、この線はutena drawingでとても見慣れた動きをもっていたからです。
(そうそれが何か音楽的なものを醸しだしてるからこそ、ひとはこの謎を解きたいと思うのかもしれません)
utena drawingのワークショップで描かれた線





バッハの線とutena drawingの線のあまりの類似
utena drawingは音楽を描き出すツール。
その仕草の中から、このバッハが描いた線とよく似た動線が登場します。もうしょっちゅうです。
utena drawingは演奏する以前の、体験する音楽。

平均律クラヴィーア曲集の表紙を描いたバッハの音楽的な仕草と、utena drawing。
バッハのあの平均律の表紙の線は、まさにまだ世に登場する前の、utena drawingだったのではないか、と言ったら言い過ぎでしょうか?
その根拠、と言えるかどうかわかりませんが、かつて、バッハより以前の音楽、グレゴリオ聖歌の指導書にはある線が描かれていました。(キロノミーと言います)
AIによる概要を引用すると
キロノミーとは、グレゴリオ聖歌の指揮法の一つで、手や指の動きを用いて旋律の動きや律動(リズム)を表現します。拍子記号のない聖歌を歌う際に、言葉のアクセントを中心に、音を高くする動き(アルシス)と低くする動き(テーシス)を空中で円を描くような形で示し、歌い手に指示を与えます。
どうでしょうね。ちょっと謎解きみたいでワクワクします。
じゃあ、その鼻歌はなんの曲だったのか、どんなモーションで描いたのか、utena drawing的な見方で眺めてみるとちょっと探偵気分です。まだ曲の断定はできないのですが・・
線と共に描かれていた文章
その表紙絵には、文章も添えられています。
”指導を求めて止まぬ音楽青年の利用と実用のため、又同様に既に今迄この研究を行ってきた人々に特別な娯楽として役立つために(徳永隆男訳)wikipedia平均律クラヴィーア曲集より”
そしてその文章は、上の渦巻きと、下の八の字の間に手書きされています。まるで上がイントロダクション、中の文章がテーマで下がコーダのようにも思えてきます。
音楽学生泣かせだった平均律クラヴィーア曲集
研究を行ってきた人々の特別な娯楽!
若い頃はこの曲集、娯楽どころか、乗り越えなければならない高い壁でした。苦悩の連続でした。タイムラグでいろんなところにずれながらメロディが入ってくるところ(いわゆるフーガ)や、跳躍の多さは、人のできる技とは思えず、非人間的なような気すらしていました。
でもなぜか何度も開いてチャレンジしてきた曲集でもあります。
二つのメロディもろくに追いかけられなかった自分の耳が、あるとき、三声のフーガのメロディが互いに戯れながら進んでいく風景を自分の演奏の中で眺められるようになったときの、急に平面が立体に立ち上がってきたような体験を教えてくれたのも、この平均律クラヴィーア曲集であり、歳を重ねながら何度も繰り返して練習してきた経験が後押ししてくれたものでした。そうか、それが特別な娯楽、なのか。確かに、何か腑に落ちるものがあります。
改めてバッハにとってこの曲集が堅苦しくなく、完成品でもなく、実用的なテキスト、(にも関わらず美しく整えられ考えられた音)そして、特別な娯楽として、作曲され、出版されたものだったことにバッハへの親しみがさらにわいてきます。そして一曲一曲、実は温かみのある楽曲であるとも今では思えるようになりました。
再び、表紙絵に・・
改めて、もう一度この表紙をながめてみませんか。

そしてここから始まるバッハから音楽を学ぶ私たちへのこのギフトに耳をすませてみてください。 バッハの鼻歌がきこえてきそうじゃないですか。
utena drawingを一緒にやってみませんか?