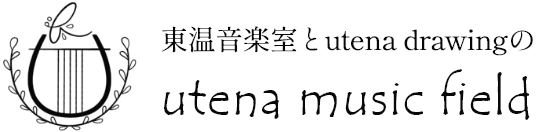昭和の歌謡曲のグルーブを体感して歌に生かす【アカシアの雨が止むとき】
アカシアの雨が止むとき(西田佐知子)
アカシアの雨が止むとき、のアカシアの花は?
以前に個人ワークで、西田佐知子の「アカシアの雨がやむとき」を歌いたいのだが・・という注文があり、私はその時初めてこの曲を知りました。ええ曲やないですか。昔の歌謡曲をドローイングするのはこのときが初めて。面白かった!
ワークの前に、花の名前がすぐ気になるので、探してみました。
西田佐知子の「アカシアの雨がやむとき」に登場するアカシアの花は、ミモザアカシア(黄色いポンポンした小さな花)ではなくて、ニセアカシアらしいです。上の写真がそのニセアカシアの写真
歌詞の一節
思い出のペンダント
白い真珠のこの肌で
寂しく今日も暖めてるのに・・
のこの、白い真珠色はこのはなの色かもしれませんね。
聞いてみる
この頃の歌は、譜割りがちょっと独特。
「うたれて」の早口とか「夜があける 日がのぼる」の粘りとか、「あのひとは」の間合い。
でも、その譜割りでも、ちゃんと拍子感があって、というか、かなりその癖のある拍子感が独特な波を作っている。
リズムに上手くのれんのよね、どうしたらいい?というの注文の主訴。
この歌を真似しようとして、リズムが取れない、ずるっとなってしまうというのは、その波がうまくつかめていないのかも。
”アカシアの雨がやむとき”をutena drawing で紐解く
ということで、 この曲のutena drawing を個人ワークで一緒にやってみました。
言葉で解析したものを伝えられないとき、そして、単にこうなっている、という正解ではなく、その人にとって納得の行く解へ結びつけていくためにutena drawing は欠かせないツールとなっています。

1拍目は少し粘りがあり、2拍目で推進力が出る4拍子。
緑の線のグルーブに乗せて歌うと、流れがつかめると思う。
拍も描きとってみる。

以外にも規則的。有機的で規則的。
そして以外にも明るい。描いてみてわかる、ということがよくあります。
この曲は人に教えられて知ったのだけど、
そういえば、少し前別の方と中山ラビの話で盛り上がった。
この頃の歌手の上手い人ってほんとにうまい。
何が、って発音にしても リズム感にしても 質感や触感がちゃんとあって、
その瞬間瞬間にそこにその人がいる感じがする。
だから、ズルズルっと歌って真似できるようなもんじゃないなあ、と、思ったのでした。
この曲、フレーズの規則性なんかなくて、情緒的に詩を連ねているように聞こえるけれども、生徒さんのワークのあとで、自分でもう一度ドローイングしてみたら、意外なことに循環するオスティナートのフォルムになったので、驚きました。いい歌の秘密って案外そんなところにあるのかも。
これ、もう一度やってみたいなあ。
アカシアの雨がやむとき
作詞:水木かおる
作曲:藤原秀行